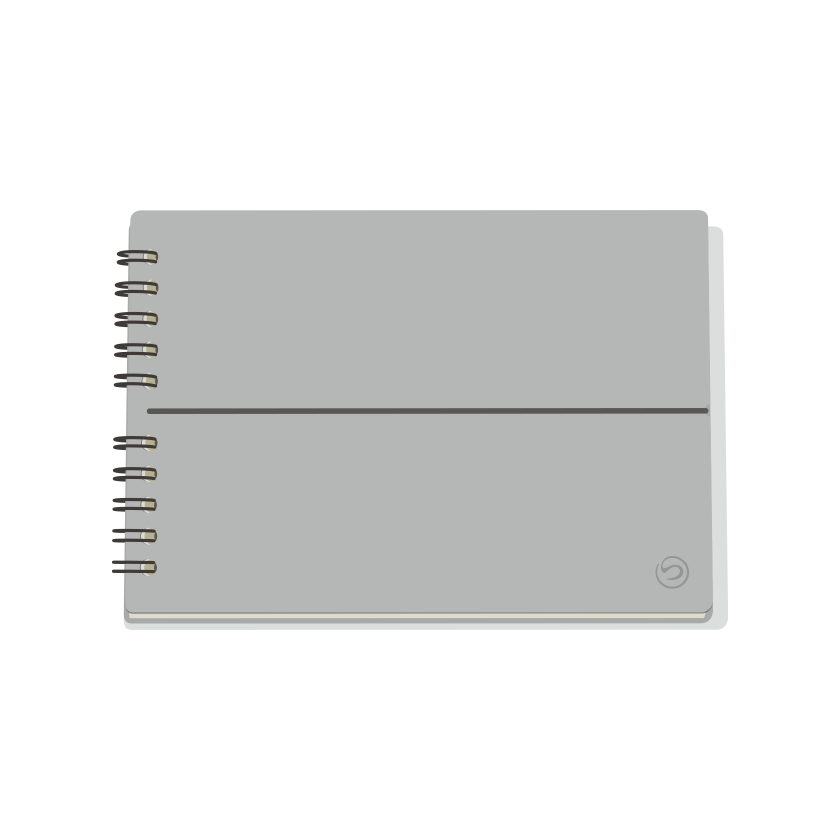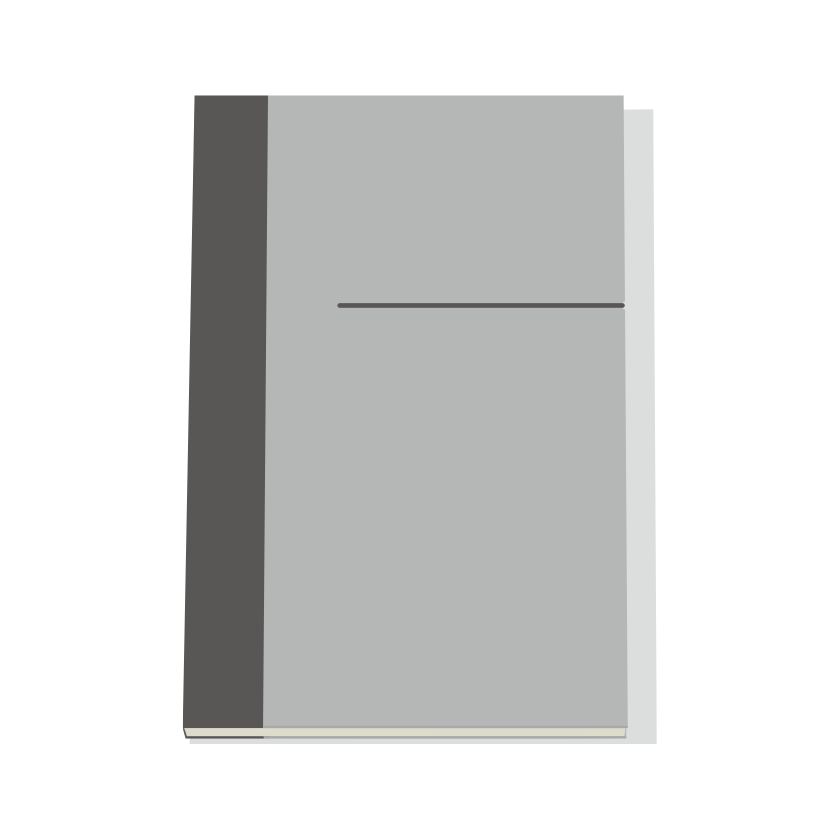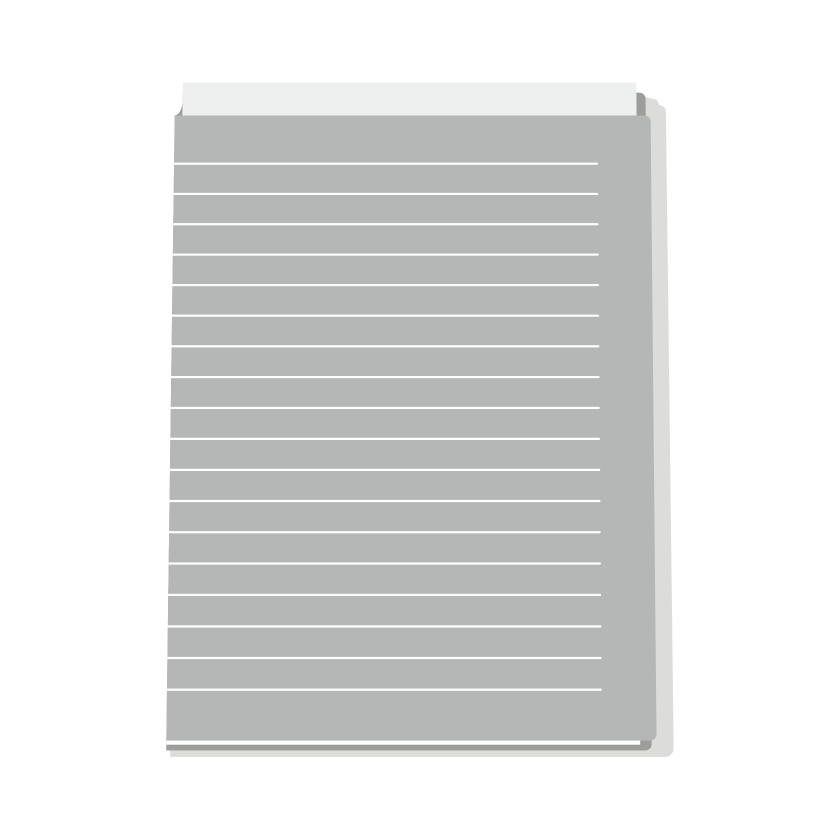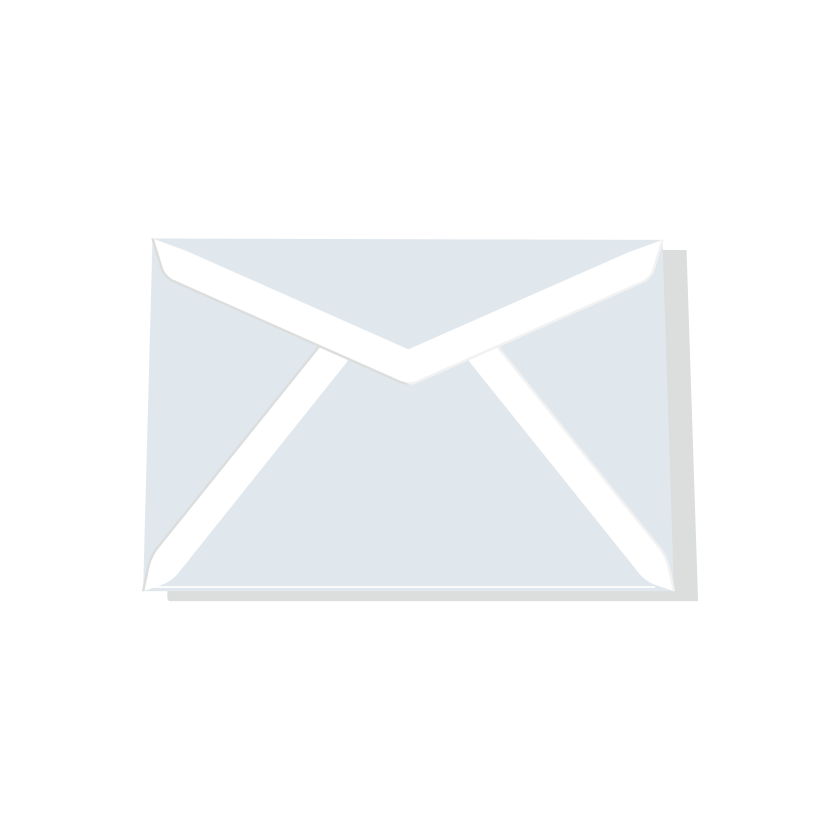つくし文具店について
つくし文具店とは
1965年頃、ぼくのおふくろが実家の片隅ではじめた「つくし文具店」。「つくし」は、おふくろの旧姓「筑紫」。JR中央線国立駅北口から歩いて20分ぐらいの住宅地にあって、近くに中学校があり、こどもたちが寄り道をして、おとなが井戸端会議するような「地域にひらかれた店」でした。
ぼくが跡をついで「つくし文具店」を再オープンしたのは、2005年6月5日。1990年に閉店して物置になっていた場所に手を入れて、3坪ほどの空間に大きな黒板をつけて小さな教室のような店になりました。住んでいる人しかいない場所に、わざわざ遠くから人が来てくれる「地域を開く店」にしたいと考えました。
ことのはじまり
そもそも「つくし文具店」を再オープンは、ドリルデザインの林裕輔さんと新宿の地下にあるバーで飲んでいる時に、林さんがぼくの家の話を面白がってくれたからです。適度な老舗感のあるまる「つ」のマーク、赤のポストと黄色の車止めとのバランスで青い旗になりました。色使いは、バウハウスを意識したそうで、デザインの学校というイメージで内装と外装ができました。
ぼくにデザイナーの知り合いが多かったことから、デザイナーの手がけた文具らしきものを並べて、文具をテーマにした展示やトークやワークショップなどを開催。はじめは個人で出版社をやっていた芳賀八恵さんとふたりで週2日しかオープンできませんでした。その後、日直制というしくみをつくって店番を増やしたことで、週6日開くことができるようになっていきました。
つながる くらしと しごと
20年ほどデザインに活用する仕事をする中で、デザインは「くらし」と「しごと」をつなげることだと考えるようになっていきました。消費する「くらし」と生産する「しごと」をつなぎ、「くらし」の場である住宅と「しごと」の場である事務所をつなぎ、「しごと」の道具としての文具を日常の「くらし」でも使える道具にしていくことを、つくし文具店は目指しています。
15周年の時には、「つくるが くらしに しみこむ」というコピーを考えて、自分たちの「くらし」に、どうやったら「つくる」ことが「しみこむ」ようになるのか試行錯誤するようになりました。消費社会から情報社会になって、そこから「創造社会」になっていくためにもデザインの力を活用する人が増え、文具が文化をデザインする道具になることを目指しています。
オリジナル文具
現在、販売しているオリジナル文具は、オープンして1年ぐらい経った時に、ドリルデザインの提案ではじまりました。わざわざ店に来てもらうためにも、長く店を続けるためにも、オリジナル文具が必要だと考えてくれました。最初は、えんぴつとノート、その後、メモや定規、便箋や封筒、ペンケース、えんぴつキャップなど、少しずつ定番にできるアイテムを増やしていきました。
当初は、つくし文具店だけで販売していましたが、小ロットといえども1店舗だけでは売り切れないので、取扱店を探したり、ネットショップを立ち上げるなどして、販売できる体制を整えていきました。いまでは全国30店舗以上のお店で取り扱ってもらえるようになり、リピートして買ってくれる人も増えました。
ちいさなデザイン教室
2012年から12年続いた「ちいさなデザイン教室」は、少人数で月1回ペースでつくし文具店に集まって、デザイン周辺の話をしながら、くらしの中でデザインを使ってできることを考えて、プロジェクトをつくる学び合いの場です。教室の生徒が、月1回日直になります。12年間で、300人くらいが卒業しています。
当初は、デザイン関係の人が多く参加していましたが、少しずつ参加する人の層が変わり、学生、企業、教育、行政、医療など幅広い立場の人たちがデザインを学びたいと考えるようになってきたことを実感しました。参加者同士のつながりも大事にしていて、中学生から定年後の人まで、年齢も住んでいるところも仕事も違う人たちの交流と学び合いの場となっていました。
実店舗の閉店とその後
2023年末でいったん実店舗を閉店した「つくし文具店」。コロナ禍もありましたが、何よりも「つくし文具店」の母屋に住んでいたおふくろが亡くなったことが大きな理由でした。ぼく自身の年齢もおふくろが店を閉じた年齢とかわらなくなり、これまでの「つくし文具店」のあり方を見直すためにも、一旦閉めて考えることにしました。
閉店後の「つくし文具店」は、まちがどデザインセンター「ツクシハウス」として、店だったスペースだけでなく庭や母屋も含めた地域に開かれた拠点として、店ではできなかったことに取り組んでいます。お店ではないですが、不定期で様々なテーマで開いていくので、タイミングがあえば、遊びに来てもらえると嬉しいです。
つくし文具店店主のこと
最後に、ぼく萩原 修(はぎわら しゅう)のことを少しだけ紹介させてください。生まれて半年で、つくし文具店ができた家に引っ越してきました。それまで結婚するまでこの家に住んでいました。地元のみふじ幼稚園をでて、国立市にある桐朋小学校・中学校・高校で学び、大学は、小平市の武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科でした。
大学卒業後は、新宿にある大日本印刷株式会社で約10年。その後転職してリビングデザインセンターOZONEという施設で約10年、暮らしのデザインに関する展覧会を企画運営。42歳で独立し、デザインを活かした様々なプロジェクトを立ち上げ育ててきました。現在は、株式会社シュウヘンカ共同代表。NPOマルイス代表理事、明星大学デザイン学部教授です。